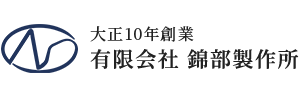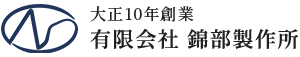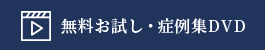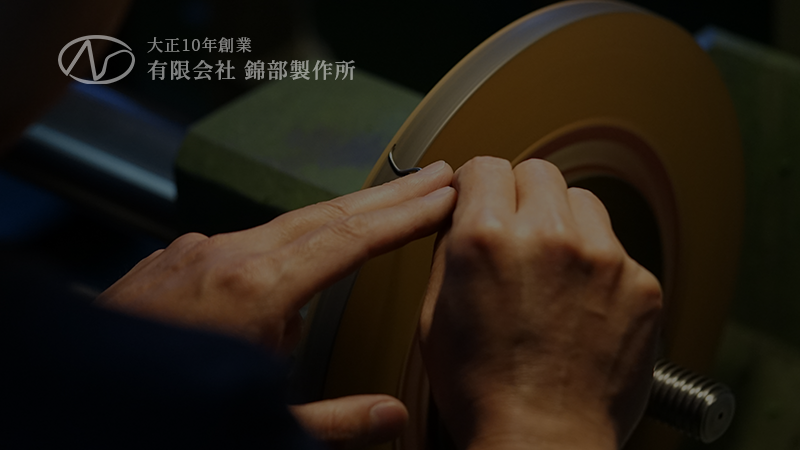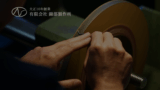超音波スケーラー用チップに求められる効果の一つとしてキャビテーション効果があります。歯周ポケットの中などでキャビテーション効果によってバイオフィルムの破壊などが期待されています。
このキャビテーション効果でどうも勘違いされていることがあります。
それは
キャビテーションが起こる超音波チップ = よく動く超音波チップ
または、
キャビテーションが起こらない = 超音波チップが動いていない
と思っている先生がいるようです。
実は、超音波チップでキャビテーション効果を得るためには2つに条件が揃わなければなりません。
その2つとは・・・・・
勘違いが起こる原因
先日、ある先生が私どもにこんな報告をしてくれました。
「スウェーデン○○○○○大学名誉教授○○○先生やその愛弟子の日本の某大学の名誉教授がビーカーの水の中で超音波チップを動かして、キャビテーション効果についてどうやら間違った情報を与えているようです」と。
これかなり抜粋ですが、要はこのスウェーデンの大学では某海外有名超音波スケーラーメーカー(A社としましょう)のものを採用したそうで、そのメーカーの超音波チップと他社(B社としましょう)の超音波チップを水の中で動かして比べて、そのA社の超音波チップはこうして良く動くがB社の超音波チップは動かないから良くないと言っているんだそうです。
う?ん。水の中での超音波スケーラー用チップの動きで善し悪しを決める。
危険な教えですね。(そして、かなり古い)
はっきり言えば、これが本当なら間違った情報なんですが、偉い大学の先生がいうと鵜呑みにされる方もいるようで、これが勘違いの原因の一つです。
せっかくですからちょっとキャビテーション効果に触れてみたいと思います。
ビーカーの水の中で超音波チップを動かして得られる情報
実はビーカーの水の中で動かす・・・・・という行為で得られる情報はたった一つです。
何だと思いますか?
水の中で超音波チップを動かしてみるというのは、超音波チップを発振させた際に水がどれだけ動くか見るということです。
ですので、回答は、そうです。キャビテーション効果があるかどうか、これだけです。
これ以上でもなければこれ以下でもないんです。
(厳密に言えば肉眼ではキャビテーション効果があるためのはじめの一歩である、水が動くかどうかを確かめる程度)
ですので、上記の偉い大学の先生が「このB者の超音波チップではキャビテーション効果は得られない」というならそれは間違いではありません。
ただし、B社のどの超音波スケーラー用チップがそうなのか正しく品名をあげて説明してくれなくてはいけません。
ですが、上記のように
キャビテーション効果がない = 超音波チップが動いていない(もしくは動きが弱い)
と言っているのならこれは著しく事実と逸脱しています。
キャビテーション効果を起こすのに必要な2つの条件
キャビテーション効果を起こすのには2つの条件が揃わなければなりません。
どうですか。何だと思いますか?
これ、超音波チップのキャビテーション効果なんて言うから難しく感じますよね。とくに超音波というあたりが味噌ですね。
なんか超音波っていうと見えないものを動かすみたいなイメージですが(実際は音として伝わる時は見えない空気を媒体にして届かせるわけですから見えないものを動かしているのですが媒体が見えないだけで、何かに触れずにものを動かすわけではないですよね。この場合も空気に触れているわけです)
で、キャビテーション効果はまずは、水の中で水を動かすわけですから、超音波は超能力ではなく、超音波チップの動きで水を直接動かすわけです。
まあ、キャビテーション効果とはちょっとかけ離れますが、原理としては人が泳いだりしてじゃばじゃば水をかくのと一緒なわけです。
この辺りを頭に入れていただくと、水を動かすために必要な条件も分かるのではないでしょうか?
いかがですか?
では回答です。
キャビテーション効果を得るために必要な条件の一つは、超音波チップがしっかりと振幅していること。
そして、もう一つは、その振幅が水に伝わりやすい形状をしていることです。
お分かりになりますか?
水は液体です。固体ではありません。
ですので超音波チップの振幅を液体である水に伝えるためには、それなりの形状になっている必要があるのです。
(超音波洗浄機などの超音波を発振させる部分もそうですよね)
実はA社の超音波チップはほとんどが振幅が水に伝わりやすい形状をしています。
これはキャビテーション効果を得るためにはいいかもしれませんが、逆にこの形状しか作れないのがA社の弱点です。
そして、B社はそうではないんですね。【ある形状】が多いんですね。それはその方が部位用途にあわせた多種多様の形状ができるからです。
しかし、この形状ではある工程が難しくなるので、A社ではこうしたものを作りたがらない、もしくは現在の製法から抜け出させずにいるので作れないのです。
キャビテーション効果だけに焦点を当てれば、これらの形状はキャビテーション効果が得られにくいです。
しかし、これは超音波スケーラー用チップが動いていないわけではないのです。
そもそも、超音波チップがどれだけ動いているかは、現在は測定器もいろいろとあり、私どもでも500万円以上する測定器でどれだけ振幅しているか測定します。
ですので、水の中で動かして、水が動かないと振動しないと言うのは非常に稚拙ですし、ましてや、片方をキャビテーションしにくい形状を選んでこうした話しをするのはB社の営業妨害にもなりかねません。(B社にはキャビテーション効果を得やすい超音波スケーラー用チップもあるのです)
まあ、とにかくこうした話しは鵜呑みにしない方が良いでしょう。
予断ですが、超音波スケーラーを選択する際に、どこどこの大学で使われているからと選ぶ先生がいます。
これはこれで一つの決定の要素だと思いますが、それだけで決めるのはとても危険です。
それは超音波スケーラーは商品です。販売されているんです。
そこには何らかの利権が絡むこともあります。
先生自身でよく考えて決めることが必要です。
超音波スケーラーでどういう治療がしたいのか、超音波スケーラーに何を求めるのか。
超音波スケーラー選びで大切なのは、
超音波スケーラー本体の性能 + 超音波チップの性能
です。